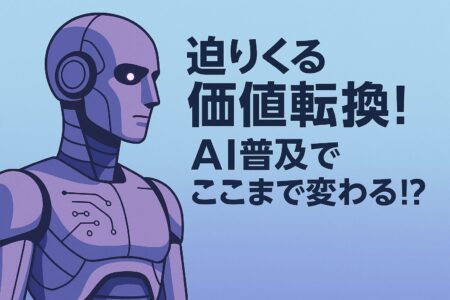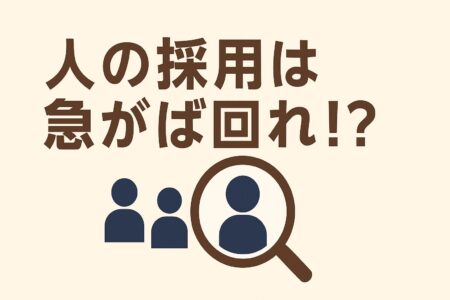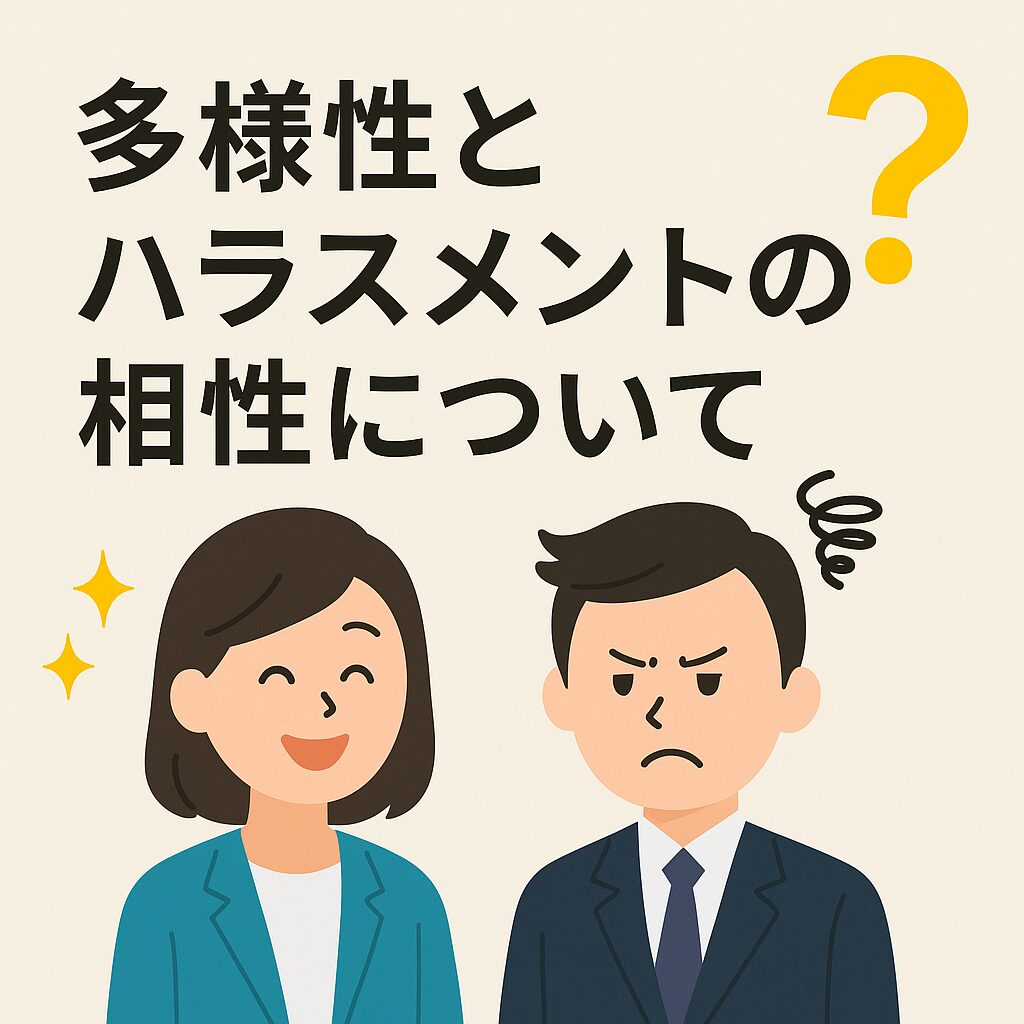
こんにちは。
パンタグラフの中谷です。
先日、島根県のとある団体にて、2日間にわたりハラスメント研修を担当させていただきました。
参加者の皆さんがとても前向きで、真剣に耳を傾けてくださる方ばかりだったのですが、
その中で、とても印象に残ったご質問がありました。
「最近、いろんなところで“多様性”って言われてますけど、
今日のハラスメントの話を聞いていると、世の中が多様化すればするほど、
ハラスメントって起きやすくなるように思えるんですが、先生はどう思われますか?」
・・・これは鋭い!と思いました。
ただ聞くだけではなく、自分ごととしてきちんと捉えてくださっていたことに、とても嬉しくなりました。
今回はこのご質問をきっかけに、
「多様性とハラスメントの相性」について考えてみたいと思います。
目次
■ 結論:多様性とハラスメントは“相性が悪い”
いきなりですが、結論から申し上げます。
多様性とハラスメントは、残念ながら相性がよくありません。
もう少し丁寧に言えば、
「多様性が進む社会で、ハラスメントを減らすことはかなり難易度が高い」ということです。
■ そもそも、ハラスメントの定義って?
ハラスメントとは簡単にいえば、
「意図的か否かを問わず、相手を不快にさせる言動」
つまり、「自分はそんなつもりじゃなかった」と思っていても、
相手が不快に感じたらハラスメントになりうる、ということですね。
■ 対する“多様性”とは?
一方、「多様性(ダイバーシティ)」とは、
背景・性別・文化・価値観などが異なる多様な人たちが、
それぞれの特性を尊重しながら共存していくこと
を意味します。
つまり「相手が自分と違っていてあたりまえ」の社会になるということです。
■ 相性の悪さの根本は「基準のズレ」
相性が悪くなる原因は、ハラスメントの定義にある
「意図的か否かを問わない」という点にあります。
背景や価値観が違えば、相手の“地雷”を知らずに踏んでしまう確率は上がります。
本人に悪意がなかったとしても、知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまうことがあるのです。
たとえば、“同質性”の高い社会(日本の過去の姿に近いかもしれません)では、
「自分が嫌なことは、相手にもしない」
という感覚がよく機能していました。
しかし、多様な社会ではどうでしょうか?
- 自分にとって「良かれ」と思ってしたことが、相手にとっては「迷惑」だったり
- 自分なら「絶対言われたくない」ことが、相手にとっては「むしろ言ってほしい」だったり
こうした“すれ違い”があたりまえに起きるのが、多様性の時代です。
■ では、どうすればいいのか?
ここでの対策は、決して複雑ではありません。
「しっかりとコミュニケーションをとること」
これに尽きます。
これまで日本では「察すること」が美徳とされてきました。
私自身も、この文化は大好きです。
でも、「察する」だけではもう限界がある。
相手とちゃんと向き合って、「あなたはどう思いますか?」「これはどう感じますか?」と、
確認してすり合わせていくことが求められます。
■ ハラスメントを減らすには、“自分視点”を疑うこと
私が特にお伝えしたいのは、
「自分たちの常識こそ正しい」という思い込み
こそが、ハラスメントの“温床”になってしまうということです。
どれだけ正しいつもりでも、それが相手にとっては攻撃に感じられるかもしれない。
そういう時代なのです。
■ 最後に
時代は確実に「多様性」へと進んでいます。
そして同時に、ハラスメントに対する社会の目も、どんどん厳しくなっています。
多様性の中でハラスメントを起こさないこと
これは非常に高いハードルではありますが、
私は、そこに向き合っていくことが自分の仕事だと考えています。
どうか、ひとりで悩まないでください。
いつでも、ご相談くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。